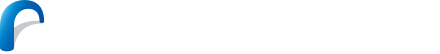教員には明確にメリットを伝え、生徒には成果を見せることで取り組みが定着。より自主的な活用が実現
自由ケ丘高等学校(福岡県)
2025.4.16
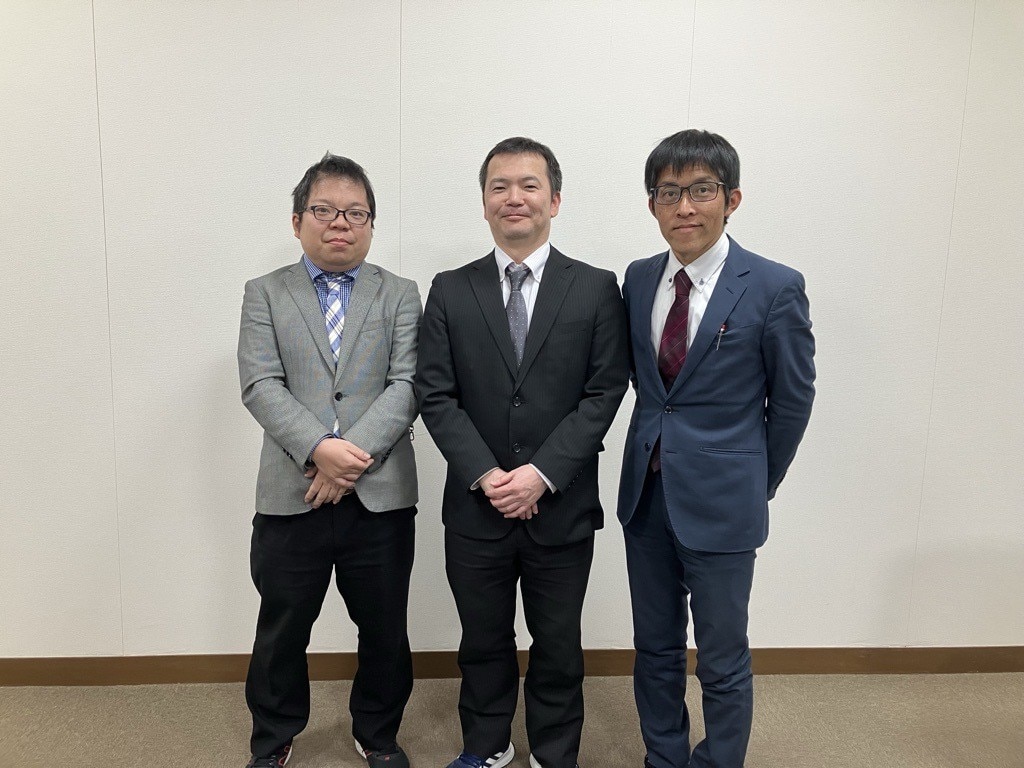
左から)進路指導部 副部長/国語科/岩本 祥吉先生、進路指導部 部長/英語科/小林 誠一先生、第1学年 主任/理科/園田 孝允先生
| 課題 |
|
|---|---|
| 活用ポイント |
|
| 活用効果 |
|
『受験サプリ』の時代から希望者対象で導入。コロナ禍を機に全校一斉導入へ
北九州市の私立高校である本校は、『スタディサプリ』の前身だった『受験サプリ』を2015年に希望者対象で導入しました。この時はまだ生徒にタブレットを持たせておらず、利用を申し込んだ生徒だけがパソコンルームに来て、通年講座の中から自分に合ったレベルの講座を受講するというスタイルでした。当時、導入を担当した先生も「便利なものがあるから使ってみよう」ぐらいの気持ちだったと聞いていますが、実際に活用しながら大学受験の成功につなげた生徒もおり、確かに良いものなんだなという印象はありました。
その後、学校全体でのタブレット導入が始まり、さらにコロナ禍をきっかけとして、全校一斉に『スタディサプリ』を導入することとなりました。当時は新入生の入学式も中止され、在校生は新学期が始まっても登校できない状況。しかし近年は、大学受験において学校推薦型選抜を希望する生徒が多く、そのために評定平均値を高めたいという生徒も増えています。評定は学校で行われる考査によって決まるため、何とか生徒たちの学びを止めないように、『スタディサプリ』の推奨動画を生徒に紹介しました。また先生方を対象とした「スタサプ研修」を行い、機能についての理解を深めるとともに、オンラインのホームルームで使ってもらうように促しました。
ただ、この時は想定外の全国一斉休校による取り急ぎの導入措置だったため、活用方法の検討や効果測定については正直なところ不十分であったと思います。登校ができるようになってから、どのように生徒の活用を進めていくのか、習熟度別に活用を定着させられるか、教員側も上手く使いこなせるか、それが本当の課題でした。
その後、学校全体でのタブレット導入が始まり、さらにコロナ禍をきっかけとして、全校一斉に『スタディサプリ』を導入することとなりました。当時は新入生の入学式も中止され、在校生は新学期が始まっても登校できない状況。しかし近年は、大学受験において学校推薦型選抜を希望する生徒が多く、そのために評定平均値を高めたいという生徒も増えています。評定は学校で行われる考査によって決まるため、何とか生徒たちの学びを止めないように、『スタディサプリ』の推奨動画を生徒に紹介しました。また先生方を対象とした「スタサプ研修」を行い、機能についての理解を深めるとともに、オンラインのホームルームで使ってもらうように促しました。
ただ、この時は想定外の全国一斉休校による取り急ぎの導入措置だったため、活用方法の検討や効果測定については正直なところ不十分であったと思います。登校ができるようになってから、どのように生徒の活用を進めていくのか、習熟度別に活用を定着させられるか、教員側も上手く使いこなせるか、それが本当の課題でした。
到達度テストと連動した課題配信機能が便利。「スタサプコンテスト」も開催
平常通り登校できるようになってからは、主に授業内で『スタディサプリ』を利用し、到達度テストも受験しています。単元テストも授業中に実施し、理解度をチェックした上で教員が解説するという流れが多いです。特に重宝しているのは、到達度テストの実施後、そのテスト範囲と連動した課題を配信できる機能です。自分の弱点克服のためにやろう!と呼びかけ、個別最適な学び直しに活用しています。
普段の大まかな活用頻度や内容は、各学年の『スタディサプリ』担当教員が計画・管理していますが、ある程度の柔軟性を持たせており、中学校範囲からやり直すクラスもあれば、英検のレベルに合わせて取り組むクラスもあります。また、小論文対策講座なども個々の進路希望に合わせて選択しています。ちなみに授業外では、自分の状況に合わせて自主的に活用してほしいとの思いから、なるべく宿題としては出さないという方針をとっています。
先生方の活用を定着させる工夫としては、まず『スタディサプリ』担当教員のほうで、高校講座の内容や機能をいま一度確認・把握しました。膨大な量の動画を確認するのは大変でしたが、最初にこれを行うことで各教科の明確なメリットを洗い出し、先生方に伝えることができたと思います。
普段の大まかな活用頻度や内容は、各学年の『スタディサプリ』担当教員が計画・管理していますが、ある程度の柔軟性を持たせており、中学校範囲からやり直すクラスもあれば、英検のレベルに合わせて取り組むクラスもあります。また、小論文対策講座なども個々の進路希望に合わせて選択しています。ちなみに授業外では、自分の状況に合わせて自主的に活用してほしいとの思いから、なるべく宿題としては出さないという方針をとっています。
先生方の活用を定着させる工夫としては、まず『スタディサプリ』担当教員のほうで、高校講座の内容や機能をいま一度確認・把握しました。膨大な量の動画を確認するのは大変でしたが、最初にこれを行うことで各教科の明確なメリットを洗い出し、先生方に伝えることができたと思います。
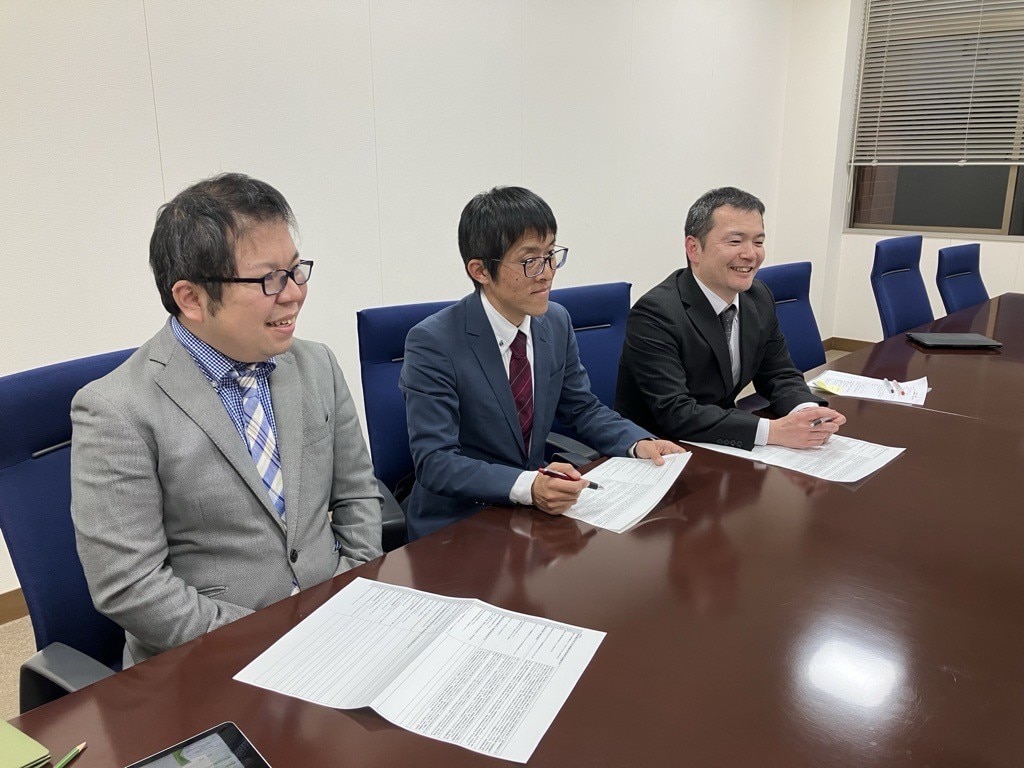
生徒に対しては、『スタディサプリ』を通して小さな成功体験を積み重ねることが更なる自主活用につながると考え、たとえば1年生では政経などの暗記科目から活用を進めました。努力の結果が出やすい政経で自信がついた生徒は、他の教科でも積極的に使おうとする姿勢が見られました。また、生徒の活用頻度を上げる目的で「スタサプコンテスト」を開催している学年もあります。当初は生徒から「コンテストに参加しようにも、講座が多すぎて何を見ればいいかわからない」という声が上がったため、推奨講座リストを作って取り組みやすくしました。
さらに、保護者の『スタディサプリ』への理解も重要と考え、保護者会では実際のテキストを一部印刷し、どのように生徒が取り組んでいるかを具体的に説明するように工夫しています。保護者向けに丁寧に説明することで、自宅学習時のフォローにも協力いただきやすいと考えています。
導入によって明らかに成績や意欲が向上。自主的に「スタサプ部」も発足
導入によって見えてきた変化としては、やはり成績アップと意欲アップ。岩本先生のクラスでは、『スタディサプリ』活用前は平均的な成績だった生徒が、活用後は校内ランキングで上位に入るようになったケースもあります。全体的な成果として、スタサプの「確認テスト」を継続した生徒は成績向上が見られたり、促進施策として始めた「スタサプコンテスト」も楽しみながら互いに切磋琢磨して取り組む生徒が増えてきました。頑張った分結果が付いてくることを実感できた生徒が、さらに頑張っている印象です。また英検にチャレンジする生徒も増加傾向にあり、相乗効果を感じています。
ユニークなところでは自主的なクラブ活動として、生徒自身が名付けた「スタサプ部」も誕生しました。週2回、生徒が集まって学習目標を立て、進捗の確認、活用方法の共有などを行っています。普段の自習時間でも、『スタディサプリ』に取り組む生徒が増え、スキマ時間にも上手く活用している実感があります。
最近は教員自身の使いこなし方も進化し、生徒の取り組みを可視化して指導につなげることはもちろん、入試情報のブラッシュアップなどにも活用するようになりました。たとえば、新任の先生に志望大学別の講座を見てもらい、傾向を掴んでもらうといった使い方ができ、教員側の教育にも役立っています。
現在は特に1年生で『スタディサプリ』の取り組みが進んでいるため、今後は全学年、同レベルで取り組みが定着するように力を入れていきます。
ユニークなところでは自主的なクラブ活動として、生徒自身が名付けた「スタサプ部」も誕生しました。週2回、生徒が集まって学習目標を立て、進捗の確認、活用方法の共有などを行っています。普段の自習時間でも、『スタディサプリ』に取り組む生徒が増え、スキマ時間にも上手く活用している実感があります。
最近は教員自身の使いこなし方も進化し、生徒の取り組みを可視化して指導につなげることはもちろん、入試情報のブラッシュアップなどにも活用するようになりました。たとえば、新任の先生に志望大学別の講座を見てもらい、傾向を掴んでもらうといった使い方ができ、教員側の教育にも役立っています。
現在は特に1年生で『スタディサプリ』の取り組みが進んでいるため、今後は全学年、同レベルで取り組みが定着するように力を入れていきます。
自由ケ丘高等学校(福岡県)
●生徒数:1年生:495人、2年生:436人、3年生:535人

関連事例
|CONTACT|
スタディサプリ学校向けサービスの導入に関する
ご質問・ご確認は、お気軽にお問い合わせください。
ご質問・ご確認は、お気軽にお問い合わせください。
就学別スタディサプリ
リクルートグループのサービス
- 転職ならリクナビNEXT
- 転職支援ならリクルートエージェント
- 女性の転職情報とらばーゆ
- 就職はリクナビ
- 就職活動はリクナビ
- 就活はリクナビダイレクト
- リクナビ派遣
- 派遣会社のリクルートスタッフィング
- 独立・開業のアントレnet
- バイト探しフロム・エーナビ
- アルバイト情報タウンワーク
- 求人転職サイトはたらいく
- フロム・エーキャリア
- 医師求人ならリクルートドクターズキャリア
- 看護師求人ならナースフル
- ケイコとマナブ.net
- じゃらんnet
- 海外旅行ならエイビーロード
- 結婚式ならゼクシィ
- 妊娠-出産-育児はゼクシィBaby
- 通販ならポンパレモール
- 不動産・住宅情報ならSUUMO
- SUUMO賃貸
- 不動産会社検索ならスマッチ
- 住宅相談はスーモカウンター
- 中古車ならカーセンサー
- ホットペッパーグルメ
- ホットペッパービューティー
- 人間ドックのここカラダ
- 海外求人・海外転職はRGF
- 家具インテリアのタブルーム
- コード評価はCodeIQ
- ゴルフ場予約じゃらんゴルフ
- POSレジアプリならAirレジ
- リクルートカード
- 関連サイト
- グループ企業一覧
- ISIZE
(C) Copyright 2020 株式会社リクルート All rights reserved.