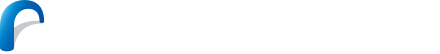進学校として「与えられたことをきちんとこなす生徒」から「自走できる生徒」への変容をサポート
鹿児島県立甲南高等学校(鹿児島県)
2025.4.10

進路支援部主任/国語科/森園 隆志先生
| 課題 |
|
|---|---|
| 活用ポイント |
|
| 活用効果 |
|
動画の質の高さや、つまずきを洗い出せることに魅力を感じて導入決定
ノーベル賞受賞者とオリンピアンの両方を輩出した日本で唯一の学校、それが本校です。2014年にノーベル物理学賞を受賞した赤﨑勇博士、2008年北京オリンピックの水泳で銅メダルを獲得した宮下純一さん、どちらも本校の卒業生です。現在も学問とスポーツの両立を重視しており、文部科学省指定のスーパーサイエンスハイスクールにも選ばれています。
教育において、日頃から大切にしているのは「自走できる生徒」を育てること。本校は毎年、国公立大学に既卒含め270名前後の合格者を輩出しており、生徒たちの学力は高めです。そのため言われたことはしっかりできるのですが、そこから一歩進み、自分に何が足りないかを把握して「自ら学ぶ」姿勢を身につけてほしいと考えています。
もともと本校では、学校教育のICT活用を支援するクラウドサービスを活用していました。ただ、それによってGoogle、Microsoftなどのアカウントやツールが乱立することとなり、かえって使いづらさを感じるようになっていました。このサービスを使い続けるかどうかを検討する中で、もっと学力向上の効果が期待でき、進路指導にも活用できる別のサービスに切り替えたほうが良いのでは…という話になりました。『スタディサプリ』の営業を受けたのは、ちょうどそんなタイミングでのことでした。
『スタディサプリ』で魅力的に感じたのは、まず講義動画です。これを見ることが、生徒にとって「自ら学ぶ」ことの第一歩になるのでは?と考えました。内容や講師陣も充実しており、教員の間で「この英語の先生、有名な方ですよね」といった声も上がりました。また、単元テストや到達度テストを活用することで、個々の生徒がどこでつまずいているかを把握できることも非常に良いと感じました。さらに、共通テストの受験者が多い本校としては、新しい「情報」の教科に対応していることも大きなポイントでした。
導入にあたっては、それまで利用していたクラウドサービスで学力診断テストも実施していたため、それが『スタディサプリ』の到達度テストに置き換わることで、「過去の成績と比較した相対把握ができなくなる」という意見も出ました。ただ、「相対把握は後からでも可能。まずは、今のつまずきがどこにあるか、きちんと把握することが重要ではないか。『スタディサプリ』ならそれができる」ということで学内の合意を得ました。現在、導入1年目ですが、以前のサービスよりも活発に使われていると感じています。リクルート社の方が来てくださり、教科会に入って先生方への説明会を開催してくださったことも積極的な活用につながったと思います。
(進路支援部主任/国語科/森園 隆志先生)
教育において、日頃から大切にしているのは「自走できる生徒」を育てること。本校は毎年、国公立大学に既卒含め270名前後の合格者を輩出しており、生徒たちの学力は高めです。そのため言われたことはしっかりできるのですが、そこから一歩進み、自分に何が足りないかを把握して「自ら学ぶ」姿勢を身につけてほしいと考えています。
もともと本校では、学校教育のICT活用を支援するクラウドサービスを活用していました。ただ、それによってGoogle、Microsoftなどのアカウントやツールが乱立することとなり、かえって使いづらさを感じるようになっていました。このサービスを使い続けるかどうかを検討する中で、もっと学力向上の効果が期待でき、進路指導にも活用できる別のサービスに切り替えたほうが良いのでは…という話になりました。『スタディサプリ』の営業を受けたのは、ちょうどそんなタイミングでのことでした。
『スタディサプリ』で魅力的に感じたのは、まず講義動画です。これを見ることが、生徒にとって「自ら学ぶ」ことの第一歩になるのでは?と考えました。内容や講師陣も充実しており、教員の間で「この英語の先生、有名な方ですよね」といった声も上がりました。また、単元テストや到達度テストを活用することで、個々の生徒がどこでつまずいているかを把握できることも非常に良いと感じました。さらに、共通テストの受験者が多い本校としては、新しい「情報」の教科に対応していることも大きなポイントでした。
導入にあたっては、それまで利用していたクラウドサービスで学力診断テストも実施していたため、それが『スタディサプリ』の到達度テストに置き換わることで、「過去の成績と比較した相対把握ができなくなる」という意見も出ました。ただ、「相対把握は後からでも可能。まずは、今のつまずきがどこにあるか、きちんと把握することが重要ではないか。『スタディサプリ』ならそれができる」ということで学内の合意を得ました。現在、導入1年目ですが、以前のサービスよりも活発に使われていると感じています。リクルート社の方が来てくださり、教科会に入って先生方への説明会を開催してくださったことも積極的な活用につながったと思います。
(進路支援部主任/国語科/森園 隆志先生)
個々の学習状況を把握しやすく、配信の進度やレベルも柔軟に変えながら活用
英語科に関して言うと、全学年で文法の理解定着に課題を感じていたのですが、授業で充分に時間を確保することが難しい状況でした。そこで、主に文法力の向上を目的として『スタディサプリ』を配信することにしました。
たとえば1年生の1学期では、まず皆が一緒に取り組んで生徒も教員も使い方に慣れていこうと、授業中に『スタディサプリ』の時間を確保。日々題(日常的に取り組ませる学習課題)として、4月に中学校英語の復習、5月は授業内容のおさらいの講座動画と確認テストを配信しました。
取組みに慣れてきた6月からは、宿題として配信し、生徒の取組みシーンを授業中から自宅学習へとシフトしました。宿題は評価対象ではありませんが、「誰が頑張ったかはこちらでも確認できるよ。自分でも正答率がわかるから、自分を知るためにやろう」と呼びかけて動機付けしていました。以前は宿題を出すにも、問題集などから授業の進度に対応する箇所を探し、印刷、配布していましたが、『スタディサプリ』ならその手間がなく、宿題を出し忘れた時もすぐ配信できます。また、欠席者のフォローアップにも役立っています。
他にも『スタディサプリ』の具体的な仕様について、英語科で「いいな」と感じたポイントを3つにまとめてみました。
①個々の状況が把握できる
学習管理画面やタイムライン機能によって、生徒それぞれの学習内容や取り組み時間がわかるので、「最近、英語に不安を感じていそうだな」「こんな夜中にやっていて心配だなぁ」などと様々な情報が得られ、最適な声かけや個別指導につながりました。担任会や学年会では、気になる生徒について取り組み状況を共有し、生徒にお声がけいただくように促したりもしました。
また生徒にとっても、自分の頑張りが蓄積・可視化されるのは楽しく、自己肯定感が上がるようです。宿題配信したら、すぐに取り組む生徒もいます。
②進度やレベルを変えられる
1教科を複数の教員で担当しているため、各クラスの進度やレベルに合わせて配信内容を変更できるのは助かります。日々題の配信内容は、単元テストの結果を踏まえてベーシックレベルかスタンダードレベルかを選択し、上位層向けにハイレベルを配信することもありました。ただ答えがわかるのではなく、“なぜそうなるのか”から理解できるように、実力に合ったレベルを選択することが大切だと感じました。
③自主学習にも活用できる
取り組める自由度が高いので、自分で苦手な単元の復習問題を探し、宿題にプラスアルファで取り組む生徒が見受けられました。やはり積極的に活用している生徒は、そのぶん理解が深まり成績も上がっています。中には、中学校で学ぶ文法さえ不安のあった生徒が、英作文がスムーズになったケースも。自分の苦手部分が解消されると『スタディサプリ』の良さが実感できるようで、他教科でも使ってみようという意欲の広がりが見られました。
(1学年主任/英語科/永山 愛子先生)
たとえば1年生の1学期では、まず皆が一緒に取り組んで生徒も教員も使い方に慣れていこうと、授業中に『スタディサプリ』の時間を確保。日々題(日常的に取り組ませる学習課題)として、4月に中学校英語の復習、5月は授業内容のおさらいの講座動画と確認テストを配信しました。
取組みに慣れてきた6月からは、宿題として配信し、生徒の取組みシーンを授業中から自宅学習へとシフトしました。宿題は評価対象ではありませんが、「誰が頑張ったかはこちらでも確認できるよ。自分でも正答率がわかるから、自分を知るためにやろう」と呼びかけて動機付けしていました。以前は宿題を出すにも、問題集などから授業の進度に対応する箇所を探し、印刷、配布していましたが、『スタディサプリ』ならその手間がなく、宿題を出し忘れた時もすぐ配信できます。また、欠席者のフォローアップにも役立っています。
他にも『スタディサプリ』の具体的な仕様について、英語科で「いいな」と感じたポイントを3つにまとめてみました。
①個々の状況が把握できる
学習管理画面やタイムライン機能によって、生徒それぞれの学習内容や取り組み時間がわかるので、「最近、英語に不安を感じていそうだな」「こんな夜中にやっていて心配だなぁ」などと様々な情報が得られ、最適な声かけや個別指導につながりました。担任会や学年会では、気になる生徒について取り組み状況を共有し、生徒にお声がけいただくように促したりもしました。
また生徒にとっても、自分の頑張りが蓄積・可視化されるのは楽しく、自己肯定感が上がるようです。宿題配信したら、すぐに取り組む生徒もいます。
②進度やレベルを変えられる
1教科を複数の教員で担当しているため、各クラスの進度やレベルに合わせて配信内容を変更できるのは助かります。日々題の配信内容は、単元テストの結果を踏まえてベーシックレベルかスタンダードレベルかを選択し、上位層向けにハイレベルを配信することもありました。ただ答えがわかるのではなく、“なぜそうなるのか”から理解できるように、実力に合ったレベルを選択することが大切だと感じました。
③自主学習にも活用できる
取り組める自由度が高いので、自分で苦手な単元の復習問題を探し、宿題にプラスアルファで取り組む生徒が見受けられました。やはり積極的に活用している生徒は、そのぶん理解が深まり成績も上がっています。中には、中学校で学ぶ文法さえ不安のあった生徒が、英作文がスムーズになったケースも。自分の苦手部分が解消されると『スタディサプリ』の良さが実感できるようで、他教科でも使ってみようという意欲の広がりが見られました。
(1学年主任/英語科/永山 愛子先生)
もともと学習に意欲的な本校の生徒が、手軽にもう一歩頑張れるツール

全教科に共通して言えることでは、やはり個々の得意・不得意が可視化され、個別最適な学習指導につながる。それが教員にとっての一番のメリットではないでしょうか。導入以前は、単元ごとの出来・不出来は見えても、他単元との縦のつながりが見えづらいところがあったのです。導入後は全体を俯瞰して日々の習熟度が見えるようになり、授業のポイントや宿題の出し方にも反映できるようになりました。
それでも、まだ細かな活用方法については改善の余地があると思います。たとえば、中下位層の生徒には単元テストを繰り返し実施しながらも、上位層にはもっと効率よく単元テストを実施し、空いた時間で自習させるなど、生徒ごとに柔軟に対応できるかもしれません。今後はさらに本校に合った活用方法をブラッシュアップし、甲南の“型”として定着していけば…と思っています。
総括すると、『スタディサプリ』は「甲南生には非常にマッチしていた」。もともと学習へのモチベーションが比較的高い本校の生徒たちにとって、「手軽にもう一歩頑張れる」ツールです。やりっぱなしにならず、個々の取り組み状況がパッと見てわかる点も非常に良かった。それによって更なる意欲が生まれるので、本校が目指す「自走できる生徒」、まさにそれを実現するきっかけやサポートになっていると感じます。今後も引き続き活用を続け、社会に出た後にも必要となる「自分で課題を見つけ、解決する力」を養っていきたいと考えています。
(進路支援部主任/国語科/森園 隆志先生)
それでも、まだ細かな活用方法については改善の余地があると思います。たとえば、中下位層の生徒には単元テストを繰り返し実施しながらも、上位層にはもっと効率よく単元テストを実施し、空いた時間で自習させるなど、生徒ごとに柔軟に対応できるかもしれません。今後はさらに本校に合った活用方法をブラッシュアップし、甲南の“型”として定着していけば…と思っています。
総括すると、『スタディサプリ』は「甲南生には非常にマッチしていた」。もともと学習へのモチベーションが比較的高い本校の生徒たちにとって、「手軽にもう一歩頑張れる」ツールです。やりっぱなしにならず、個々の取り組み状況がパッと見てわかる点も非常に良かった。それによって更なる意欲が生まれるので、本校が目指す「自走できる生徒」、まさにそれを実現するきっかけやサポートになっていると感じます。今後も引き続き活用を続け、社会に出た後にも必要となる「自分で課題を見つけ、解決する力」を養っていきたいと考えています。
(進路支援部主任/国語科/森園 隆志先生)
鹿児島県立甲南高等学校(鹿児島県)
●生徒数:1年生:321人、2年生:316人、3年生:312人

関連事例
|CONTACT|
スタディサプリ学校向けサービスの導入に関する
ご質問・ご確認は、お気軽にお問い合わせください。
ご質問・ご確認は、お気軽にお問い合わせください。
就学別スタディサプリ
リクルートグループのサービス
- 転職ならリクナビNEXT
- 転職支援ならリクルートエージェント
- 女性の転職情報とらばーゆ
- 就職はリクナビ
- 就職活動はリクナビ
- 就活はリクナビダイレクト
- リクナビ派遣
- 派遣会社のリクルートスタッフィング
- 独立・開業のアントレnet
- バイト探しフロム・エーナビ
- アルバイト情報タウンワーク
- 求人転職サイトはたらいく
- フロム・エーキャリア
- 医師求人ならリクルートドクターズキャリア
- 看護師求人ならナースフル
- ケイコとマナブ.net
- じゃらんnet
- 海外旅行ならエイビーロード
- 結婚式ならゼクシィ
- 妊娠-出産-育児はゼクシィBaby
- 通販ならポンパレモール
- 不動産・住宅情報ならSUUMO
- SUUMO賃貸
- 不動産会社検索ならスマッチ
- 住宅相談はスーモカウンター
- 中古車ならカーセンサー
- ホットペッパーグルメ
- ホットペッパービューティー
- 人間ドックのここカラダ
- 海外求人・海外転職はRGF
- 家具インテリアのタブルーム
- コード評価はCodeIQ
- ゴルフ場予約じゃらんゴルフ
- POSレジアプリならAirレジ
- リクルートカード
- 関連サイト
- グループ企業一覧
- ISIZE
(C) Copyright 2020 株式会社リクルート All rights reserved.