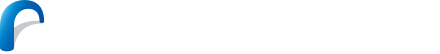より良い授業の在り方を目指し、基礎的な概念理解を講義動画でサポート
教員が重点指導すべき内容に注力し、授業の質を向上
八丈町立三原中学校(東京都)
2025.2.20

写真左から 数学/鈴木先生、校長/石井先生、理科/片平先生
| 課題 |
|
|---|---|
| 活用ポイント |
|
| 活用効果 |
|
生徒ごとの学力差が大きく、個別対応が欠かせない状況に対し、より良い授業のあり方を模索
本校は、八丈島に位置する生徒数22名、教員数14名の中学校です。生徒たちは幼稚園からほぼ同じメンバーで学校生活を送っており、お互いの学力や成長過程を理解し合った親密な関係を築いています。上級生が下級生の面倒を見る文化が根付いており、学年を超えた交流も自然に行われています。
一方で、周囲の環境が変わらないため、年次を節目に「頑張るぞ!」という意欲が生まれにくい状況です。生徒たちは、長い年月を同じメンバーと過ごす中で役割が固定化されやすく、中学校生活で新たなスタートを切るという意識を持ちにくい傾向にあります。
私たち教員としては、生徒に主体的な学習姿勢を養ってほしいという思いが強くあり、探究学習や総合的な学習を重視した取り組みを進めてきました。本校校長からも、授業のあり方を再考する方針が常々示されています。
一方で、周囲の環境が変わらないため、年次を節目に「頑張るぞ!」という意欲が生まれにくい状況です。生徒たちは、長い年月を同じメンバーと過ごす中で役割が固定化されやすく、中学校生活で新たなスタートを切るという意識を持ちにくい傾向にあります。
私たち教員としては、生徒に主体的な学習姿勢を養ってほしいという思いが強くあり、探究学習や総合的な学習を重視した取り組みを進めてきました。本校校長からも、授業のあり方を再考する方針が常々示されています。

学力に関しては、生徒数が少ないことからクラス内で極端な二極化は見られないものの、個人差が大きく、授業中には個別の対応が求められることもありました。また、本校が抱える課題の一つとして、一部生徒の家庭学習の習慣が定着していない点が挙げられます。これまで宿題として出していた紙のワークでは、各問題に紐づいた解説のみが提供されており、基礎を理解できていない生徒にとっては、全体を理解することが難しく、それにより学習自体を面倒に感じてしまうという状況でした。
こうした課題解決のため、学内で様々なICT教材を比較検討し、スタディサプリの導入を決定しました。講義動画の質の高さと、生徒が集中して視聴できる適切な長さが決め手となりました。
生徒がどこにつまずいているかを見極め、ピンポイントの動画視聴を促す
現在は、理科、数学、社会の学習においてスタディサプリを活用しています。主な目的は、授業内容の復習と定着です。また、長期休暇中の課題としても活用しており、冬休みには2学期の学習範囲をまとめて配信し、生徒が自分のペースで復習に取り組めるようにしました。一方で3年生に対しては、受験対策として、授業で追い付いていない範囲や頻出範囲を先んじて学習できるように、課題を配信することもあります。
教科・学年横断的な学習で、スタディサプリが役立つことも多いです。例えば、理科の地震の単元で、「地震の伝わる速度から到達時間を導き出す」という問題をうまく解けない生徒がいます。地震の初期微動(P波)、主要動(S波)の順で振動が伝わることは理解できているものの、「道のり÷速さ=時間」という概念が不足している、あるいは計算そのものができないというケースです。そのような場合、小学校範囲の算数の動画を配信して、復習させています。
教科・学年横断的な学習で、スタディサプリが役立つことも多いです。例えば、理科の地震の単元で、「地震の伝わる速度から到達時間を導き出す」という問題をうまく解けない生徒がいます。地震の初期微動(P波)、主要動(S波)の順で振動が伝わることは理解できているものの、「道のり÷速さ=時間」という概念が不足している、あるいは計算そのものができないというケースです。そのような場合、小学校範囲の算数の動画を配信して、復習させています。

こうした「生徒がどこにつまずいているのか」の分析・把握は特に大切にする点です。問題演習の結果を参考にしながら、生徒との対話を通して理解度を確認します。生徒は自分でどこが分からないのかを把握できていないことも多いので、それを見極めるのは教員の重要な役割だと思っています。その上で、ピンポイントで学び直しができるように動画視聴を促すなどのサポートを行います。
家庭学習においても、スタディサプリによる宿題配信を通した習慣づけに取り組んでいます。「家で勉強するのは面倒」と感じる生徒が多い中、解答方法が選択式であるという手軽さは、家庭学習を始めるきっかけとしては効果的です。また、理解度に応じて動画をスキップして問題に進めるため、生徒は自分のペースで学ぶことができ、取り組みやすさにつながっているようです。
生徒自身が自分の弱点を把握。家庭学習を充実させ、安心して学べる環境を実現
生徒の学習に対する姿勢には、少しずつ変化が見られています。生徒たちは自分の学習を振り返り、苦手部分を「メタ認知」できるようになり、その箇所を重点的に学び直すようになりました。従来のように最初から全てを復習するのではなく、スタディサプリで自分の弱点に特化した学習に取り組む様子が見られます。また、私たち教員もそうした取り組み状況を、学習履歴画面からリアルタイムで確認できます。
各問題に紐づいた解説のみがある紙のワークとは異なり、全学年の5教科の講義動画を視聴できる点もメリットです。スタディサプリを家庭学習で活用することは、ボタン一つで何でも質問できる家庭教師がいるような安心感を生徒に与えており、家庭学習における生徒間の格差は小さくなったと考えています。
教員の役割にも変化がありました。これまでは本来の単元とは異なる基礎的な内容も授業で説明していましたが、それをスタディサプリの講義動画に任せられるようになりました。例えば、理科の授業で解説していた算数の計算について、生徒はまず動画を視聴し、分からない点があれば個別に質問するという流れがつくれています。体調不良などで欠席が続いた生徒に対しても、「まずは動画を見てみて」と伝え、基本的な概念理解はスタディサプリに委ね、実験などの実践的な部分は教員が一緒に行うという役割分担ができています。スタディサプリを「分身」として活用することで、本来重点的に指導すべき内容により多くの時間を割き、授業の質を向上させることができます。
生徒には、単にテストで点数を取るためだけではなく、日常生活やさまざまな場面で活用できる「生きた知識」を養ってほしいと考えています。そして私たち教員も、そのことを常に意識し、ただ知識を教えるだけでなく、一人ひとりのつまずきを理解し、適切な学習を支援していきたいと思います。
各問題に紐づいた解説のみがある紙のワークとは異なり、全学年の5教科の講義動画を視聴できる点もメリットです。スタディサプリを家庭学習で活用することは、ボタン一つで何でも質問できる家庭教師がいるような安心感を生徒に与えており、家庭学習における生徒間の格差は小さくなったと考えています。
教員の役割にも変化がありました。これまでは本来の単元とは異なる基礎的な内容も授業で説明していましたが、それをスタディサプリの講義動画に任せられるようになりました。例えば、理科の授業で解説していた算数の計算について、生徒はまず動画を視聴し、分からない点があれば個別に質問するという流れがつくれています。体調不良などで欠席が続いた生徒に対しても、「まずは動画を見てみて」と伝え、基本的な概念理解はスタディサプリに委ね、実験などの実践的な部分は教員が一緒に行うという役割分担ができています。スタディサプリを「分身」として活用することで、本来重点的に指導すべき内容により多くの時間を割き、授業の質を向上させることができます。
生徒には、単にテストで点数を取るためだけではなく、日常生活やさまざまな場面で活用できる「生きた知識」を養ってほしいと考えています。そして私たち教員も、そのことを常に意識し、ただ知識を教えるだけでなく、一人ひとりのつまずきを理解し、適切な学習を支援していきたいと思います。
八丈町立三原中学校(東京都)
●生徒数:1学年6名 2学年6名 3学年10名

関連事例
|CONTACT|
スタディサプリ学校向けサービスの導入に関する
ご質問・ご確認は、お気軽にお問い合わせください。
ご質問・ご確認は、お気軽にお問い合わせください。
就学別スタディサプリ
リクルートグループのサービス
- 転職ならリクナビNEXT
- 転職支援ならリクルートエージェント
- 女性の転職情報とらばーゆ
- 就職はリクナビ
- 就職活動はリクナビ
- 就活はリクナビダイレクト
- リクナビ派遣
- 派遣会社のリクルートスタッフィング
- 独立・開業のアントレnet
- バイト探しフロム・エーナビ
- アルバイト情報タウンワーク
- 求人転職サイトはたらいく
- フロム・エーキャリア
- 医師求人ならリクルートドクターズキャリア
- 看護師求人ならナースフル
- ケイコとマナブ.net
- じゃらんnet
- 海外旅行ならエイビーロード
- 結婚式ならゼクシィ
- 妊娠-出産-育児はゼクシィBaby
- 通販ならポンパレモール
- 不動産・住宅情報ならSUUMO
- SUUMO賃貸
- 不動産会社検索ならスマッチ
- 住宅相談はスーモカウンター
- 中古車ならカーセンサー
- ホットペッパーグルメ
- ホットペッパービューティー
- 人間ドックのここカラダ
- 海外求人・海外転職はRGF
- 家具インテリアのタブルーム
- コード評価はCodeIQ
- ゴルフ場予約じゃらんゴルフ
- POSレジアプリならAirレジ
- リクルートカード
- 関連サイト
- グループ企業一覧
- ISIZE
(C) Copyright 2020 株式会社リクルート All rights reserved.