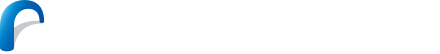宿題を出さない方針のもと、声掛けと任意課題で生徒の自学自習を支え、
島しょ部においても生徒の学習保障を実現
今治市立大三島中学校(愛媛県)
2024.12.24
カテゴリー:

| 課題 |
|
|---|---|
| 活用ポイント |
|
| 活用効果 |
|
島しょ部が抱える学習課題への対策として、スタディサプリに寄せた期待
本校は、愛媛県今治市の大三島に位置する、全校生徒66名ほどの小規模校です。自然豊かな環境で穏やかに過ごし、素直でよく指示を聞く生徒たちが多いのが特徴です。各学年1クラスのみでクラス替えはなく、生徒たちは同じ仲間と長い時間を過ごします。一方、こうした環境のため、周辺に塾が少なく、学校以外で学習する機会が得にくいといった課題がありました。
このような状況の中、2023年4月以降、今治市内の全14中学校で導入されたのがスタディサプリでした。今治市は、特に中学生においては、家庭学習が十分に行えていないという課題がありました。また、本校のような島しょ部の学校における学習保障という目的もありました。スタディサプリの動画教材やドリル教材の活用によって、生徒一人一人の学習ニーズに対応し、基礎学力向上につなげることが市としての大きなねらいです。
本校では、スタディサプリの導入によって生徒の自学自習の促進ができること、特に「何から手をつけていいか分からない」スローラーナーの学び直しの機会となることを期待しました。また、経済的に塾に通うことが難しい生徒にも、自学自習の新たな手段を提供することができます。同時に、教育界で著名な講師がプログラム開発に加わり、講義動画を担当していると聞いていたため、学習意欲の高いファストラーナーにも有効なツールとなるのではと考えていました。
このような状況の中、2023年4月以降、今治市内の全14中学校で導入されたのがスタディサプリでした。今治市は、特に中学生においては、家庭学習が十分に行えていないという課題がありました。また、本校のような島しょ部の学校における学習保障という目的もありました。スタディサプリの動画教材やドリル教材の活用によって、生徒一人一人の学習ニーズに対応し、基礎学力向上につなげることが市としての大きなねらいです。
本校では、スタディサプリの導入によって生徒の自学自習の促進ができること、特に「何から手をつけていいか分からない」スローラーナーの学び直しの機会となることを期待しました。また、経済的に塾に通うことが難しい生徒にも、自学自習の新たな手段を提供することができます。同時に、教育界で著名な講師がプログラム開発に加わり、講義動画を担当していると聞いていたため、学習意欲の高いファストラーナーにも有効なツールとなるのではと考えていました。
テスト対策や授業の補完に講義動画を役立てられるよう積極的に声掛け
もともと本校では、生徒の自主性を重視し、平時も長期休暇中も、宿題は原則として出さない方針をとってきました。スタディサプリにおいても学校全体での活用方針は定めておらず、あくまで自学自習の学習手段の一つとして、生徒の自主的な活用に任せています。
その一方、各教科の教師は必要に応じて、スタディサプリの特定の単元を「おすすめ講座」として、提出を求めない任意課題の形で配信しています。定期テスト前の効果的な対策や、テスト後に理解できていなかった部分の復習を促すためです。教科書を読む、プリントの問題を解く、といった従来の学び方を苦手とする生徒にとっては、単元ごとにまとまった動画で視覚的に学ぶことができるため、学習手段の選択肢の一つとなっています。
また、特別支援学級の生徒や学校に通うことが難しい生徒のサポートにもスタディサプリを活用しています。学級担任が、自分の担当教科以外であっても「この動画を見てみよう」と声を掛けやすく、個別の学習支援につながっています。
英語科では、学習指導要領の改訂によって議論や対話的な学びが重視されるようになり、従来のように文法説明などの時間が取りづらい状況にあります。そのため、「文法を詳しく知りたい人はこの動画を参考にして」と講義動画の視聴を呼び掛け、知識・技能の定着をスタディサプリで補完しています。単に学習ツールを提供して終わりとするのではなく、自学自習が進むような積極的な声掛けを日常的に行っています。
その一方、各教科の教師は必要に応じて、スタディサプリの特定の単元を「おすすめ講座」として、提出を求めない任意課題の形で配信しています。定期テスト前の効果的な対策や、テスト後に理解できていなかった部分の復習を促すためです。教科書を読む、プリントの問題を解く、といった従来の学び方を苦手とする生徒にとっては、単元ごとにまとまった動画で視覚的に学ぶことができるため、学習手段の選択肢の一つとなっています。
また、特別支援学級の生徒や学校に通うことが難しい生徒のサポートにもスタディサプリを活用しています。学級担任が、自分の担当教科以外であっても「この動画を見てみよう」と声を掛けやすく、個別の学習支援につながっています。
英語科では、学習指導要領の改訂によって議論や対話的な学びが重視されるようになり、従来のように文法説明などの時間が取りづらい状況にあります。そのため、「文法を詳しく知りたい人はこの動画を参考にして」と講義動画の視聴を呼び掛け、知識・技能の定着をスタディサプリで補完しています。単に学習ツールを提供して終わりとするのではなく、自学自習が進むような積極的な声掛けを日常的に行っています。

(写真)左:角尾校長先生、右:八木先生(英語科)
生徒の自学自習を効果的にサポートしながら、教師の負担軽減にも
導入2年目となり、生徒には各自が必要に応じて動画を視聴する習慣が定着してきています。テスト前の自習時間にスタディサプリを活用している生徒もおり、様々な手段がある中で自分に合った学習方法として選んでいるのだという手応えを感じます。宿題配信数に関わらず、動画視聴時間が長いのは本校の特徴といえるかもしれません。特に、何を勉強していいか分からず問題集の解答を写すだけだったスローラーナーの生徒に、「分からなかったらまずは動画の視聴から始める」という変化が見られるようになりました。
また、生徒が動画の講師陣に親しみを感じ、影響を受けている様子も見受けられるようになりました。社会科の授業では、生徒自身が先生役を務める学び合いのスタイルを取り入れていますが、スタディサプリの講師の教え方を参考に、説明の仕方や板書の構成を工夫する生徒が少なくないようです。
さらに、私たち教師の業務改善につながった側面もあります。急な出張などで授業ができない際、スタディサプリを自習教材として指定することで、自習用のプリント作成などの時間を削減できるようになりました。負担を軽減しながら生徒の学びをサポートし、島しょ部という環境においての学習保障など、スタディサプリは私たちが教育活動に取り組む上での「お守り」になっていると感じます。
ICTツールは意見の集約をスムーズにし、学習にゲーム要素を取り入れやすいのが特徴です。私たち教師も新しいツールを積極的に試し、活かす姿勢を生徒に見せていく必要があります。ICTを活用することにより、これは紙媒体でやった方がいいなどアナログの重要性にも気付くことができ、教師側も教え方をアップデートできます。教師がまず活用することで、指導力をより向上し、生徒にもいい影響を与えていきたい。教師の役割とは、「教える+魅せる」ことだと考えています。「いろんなツールを使いこなせる大人ってすごい」「自分も真似したい」と生徒に思ってもらえるよう、日々チャレンジを重ねていきたいと考えています。
また、生徒が動画の講師陣に親しみを感じ、影響を受けている様子も見受けられるようになりました。社会科の授業では、生徒自身が先生役を務める学び合いのスタイルを取り入れていますが、スタディサプリの講師の教え方を参考に、説明の仕方や板書の構成を工夫する生徒が少なくないようです。
さらに、私たち教師の業務改善につながった側面もあります。急な出張などで授業ができない際、スタディサプリを自習教材として指定することで、自習用のプリント作成などの時間を削減できるようになりました。負担を軽減しながら生徒の学びをサポートし、島しょ部という環境においての学習保障など、スタディサプリは私たちが教育活動に取り組む上での「お守り」になっていると感じます。
ICTツールは意見の集約をスムーズにし、学習にゲーム要素を取り入れやすいのが特徴です。私たち教師も新しいツールを積極的に試し、活かす姿勢を生徒に見せていく必要があります。ICTを活用することにより、これは紙媒体でやった方がいいなどアナログの重要性にも気付くことができ、教師側も教え方をアップデートできます。教師がまず活用することで、指導力をより向上し、生徒にもいい影響を与えていきたい。教師の役割とは、「教える+魅せる」ことだと考えています。「いろんなツールを使いこなせる大人ってすごい」「自分も真似したい」と生徒に思ってもらえるよう、日々チャレンジを重ねていきたいと考えています。
今治市立大三島中学校(愛媛県)
●生徒数:1学年22名 2学年24名 3学年20名

関連事例
|CONTACT|
スタディサプリ学校向けサービスの導入に関する
ご質問・ご確認は、お気軽にお問い合わせください。
ご質問・ご確認は、お気軽にお問い合わせください。
就学別スタディサプリ
リクルートグループのサービス
- 転職ならリクナビNEXT
- 転職支援ならリクルートエージェント
- 女性の転職情報とらばーゆ
- 就職はリクナビ
- 就職活動はリクナビ
- 就活はリクナビダイレクト
- リクナビ派遣
- 派遣会社のリクルートスタッフィング
- 独立・開業のアントレnet
- バイト探しフロム・エーナビ
- アルバイト情報タウンワーク
- 求人転職サイトはたらいく
- フロム・エーキャリア
- 医師求人ならリクルートドクターズキャリア
- 看護師求人ならナースフル
- ケイコとマナブ.net
- じゃらんnet
- 海外旅行ならエイビーロード
- 結婚式ならゼクシィ
- 妊娠-出産-育児はゼクシィBaby
- 通販ならポンパレモール
- 不動産・住宅情報ならSUUMO
- SUUMO賃貸
- 不動産会社検索ならスマッチ
- 住宅相談はスーモカウンター
- 中古車ならカーセンサー
- ホットペッパーグルメ
- ホットペッパービューティー
- 人間ドックのここカラダ
- 海外求人・海外転職はRGF
- 家具インテリアのタブルーム
- コード評価はCodeIQ
- ゴルフ場予約じゃらんゴルフ
- POSレジアプリならAirレジ
- リクルートカード
- 関連サイト
- グループ企業一覧
- ISIZE
(C) Copyright 2020 株式会社リクルート All rights reserved.