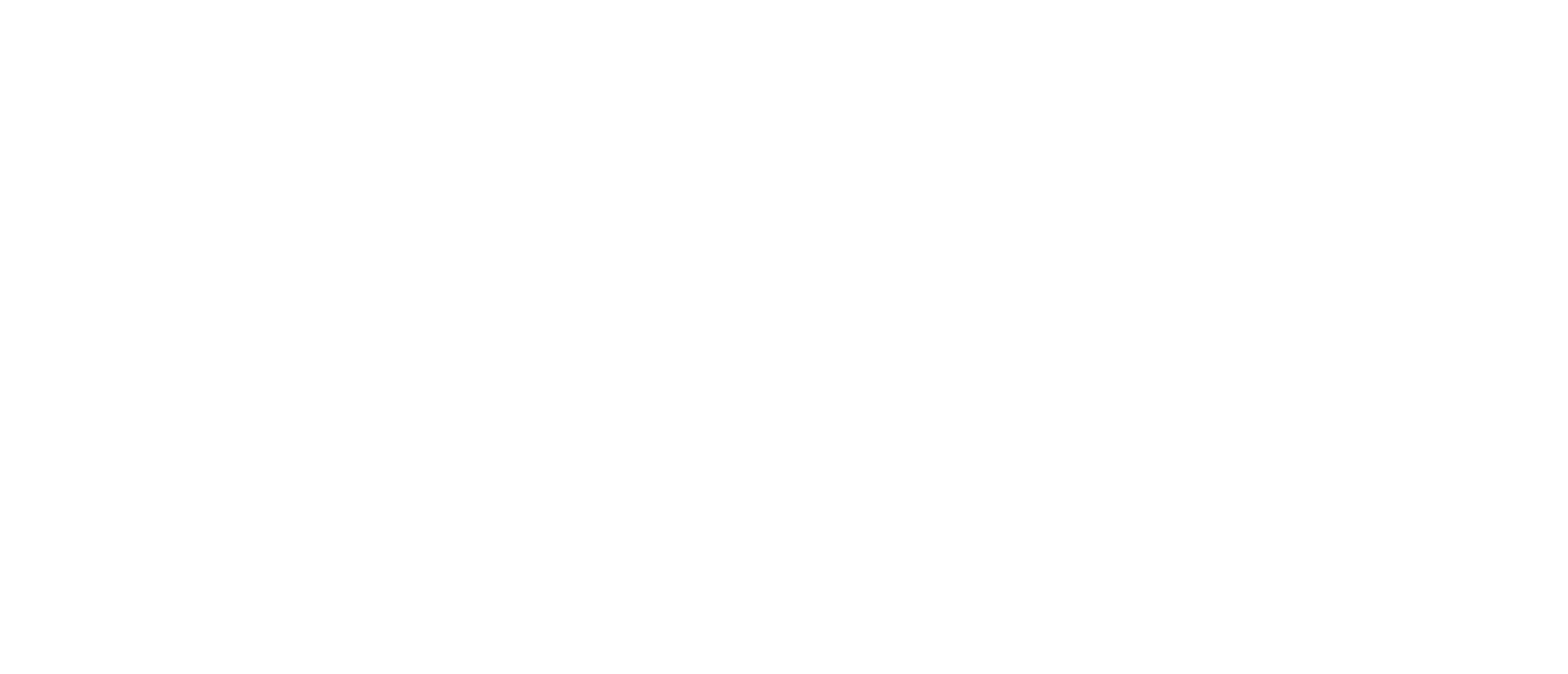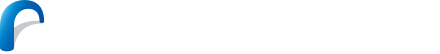授業の定着と既習範囲の学び直しのため導入。自学自習のきっかけになり、知識欲も向上
清教学園高等学校(大阪府)
2020.01.29
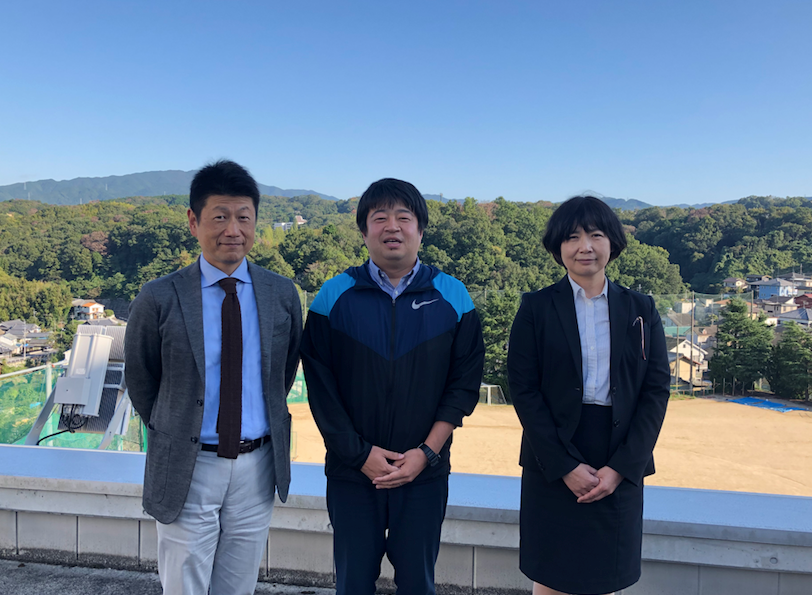
スタディサプリご担当:安藤先生・冠先生・大野先生
| 課題 |
|
|---|---|
| 活用ポイント |
|
| 活用効果 |
|
新しい取り組みを後押しする
スタディサプリのクオリティ
本校がスタディサプリを導入するきっかけになったのは2017年。学校として、生徒に個人用の情報端末を持たせることが決まったとき、インターネット上のポートフォリオ利用や学習補助ツールとして、スタディサプリが候補にあがったのです。ただ、さまざまな意見から、最終的に導入したのは手軽さが魅力の他社ツールとなりました。その後、運用の見直しがあった際に、スタディサプリの豊富なサービス内容や、生徒や教師にとっての使いやすさを改めて認識。各教科が必要としている学び直しにも、うまく活用できそうだと感じました。その流れから再検討ののちに導入に至り、昨年度の1年生・2年生から活用を開始しました。
他社も含め、多々ある学習補助ツールの中から、改めてスタディサプリを選んだのは、教材としての圧倒的な質の高さ。一見似た感じのツールは他にもあるかもしれません。でも、各単体のサービスとして比べたら、スタディサプリのクオリティの高さは他を抜きん出ていました。講義動画だけ見ても、テンポが良くてわかりやすく、時にユーモアさえ感じます。学習効果はもちろん、生徒がひとりで学ぶための自学自習ツールとしても、親しみを持ってもらえるのではと思いました。
他社も含め、多々ある学習補助ツールの中から、改めてスタディサプリを選んだのは、教材としての圧倒的な質の高さ。一見似た感じのツールは他にもあるかもしれません。でも、各単体のサービスとして比べたら、スタディサプリのクオリティの高さは他を抜きん出ていました。講義動画だけ見ても、テンポが良くてわかりやすく、時にユーモアさえ感じます。学習効果はもちろん、生徒がひとりで学ぶための自学自習ツールとしても、親しみを持ってもらえるのではと思いました。
活用を通して現れ始めた変化の数々
生徒は少しずつ自立した学習者に
現在のスタディサプリの主な活用目的は、教科ごとに異なります。例えば、数学は過去の学び直しと現在の授業内容の定着、英語は前学年の範囲の学び直しと、既習範囲の抜け落ちのフォローアップがメイン、といった具合です。各教科、火・木・金曜日に小テスト(確認テスト)を実施しています。
数学では週に1度終礼時に、教員4名が作成するオリジナル版の確認テストを行なっていますが、ここで6割以上取れたら合格としています。この小テストの範囲に該当するスタディサプリの問題を「講義動画+確認テスト」として配信し、不合格者は必須で、合格者は任意で小テストを受け、翌週の月曜日までに提出するよう指導しています。スタディサプリの問題はクラスごとではなく、学年の全生徒に対して配信することで、教員の業務負担を軽減しています。配信内容は、まず教員が講義動画を見て紐づく箇所を選定。範囲についてはコースの進度に合わせて、授業で行なった範囲を1~2講義分配信しています。また、生徒の取り組み状況はExcelでダウンロードし、確認テストの結果と照合しています。
2学年の英語では、1年次に学んだ範囲の復習として、自学用の教材を配布しています。ただ、そのまま渡すだけでは生徒は活用してくれません。活用度と生徒のやる気を高めるために、配布教材の内容を定期テストの範囲と連動させています。具体的には、週ごとに、配布教材の該当範囲に合わせてスタディサプリの「講義動画+確認テスト」を配信し、その後小テストを実施。小テスト内容の7~8割はチェックテストからで、2~3割は1年次の教材から引用。既に宿題で確認テストには取り組んでいるので、類問であるチェックテストを使用。また選択問題のほかに「自分で考えて書かせる」タイプの問題も出題し、バランスを取っています。
この確認テストは平常点にも加味しているので、生徒も真剣に臨んでいるようです。また、これらの週ベースの確認テストや定期テストの範囲に、1年次の復習要素を含めることは、既習範囲の定着にも役立っています。生徒の講義動画の視聴スタイルは、先に確認テストを行い、わからなかった箇所のみを見る反転スタイルを採用しています。時間を効率的に使うには、このようなやり方も良いのかもしれません。
また、各教科のスタディサプリの活用頻度や宿題の分量は、担当教員の裁量に任せています。提出をしない生徒に対しては、担任から声かけ。教科の担当が未提出の生徒をリスト化して担任に渡し、担任から直に生徒へ声かけしてもらう流れです。改善が見られない生徒に対しては、居残り補習をさせるケースもあります。
数学では週に1度終礼時に、教員4名が作成するオリジナル版の確認テストを行なっていますが、ここで6割以上取れたら合格としています。この小テストの範囲に該当するスタディサプリの問題を「講義動画+確認テスト」として配信し、不合格者は必須で、合格者は任意で小テストを受け、翌週の月曜日までに提出するよう指導しています。スタディサプリの問題はクラスごとではなく、学年の全生徒に対して配信することで、教員の業務負担を軽減しています。配信内容は、まず教員が講義動画を見て紐づく箇所を選定。範囲についてはコースの進度に合わせて、授業で行なった範囲を1~2講義分配信しています。また、生徒の取り組み状況はExcelでダウンロードし、確認テストの結果と照合しています。
2学年の英語では、1年次に学んだ範囲の復習として、自学用の教材を配布しています。ただ、そのまま渡すだけでは生徒は活用してくれません。活用度と生徒のやる気を高めるために、配布教材の内容を定期テストの範囲と連動させています。具体的には、週ごとに、配布教材の該当範囲に合わせてスタディサプリの「講義動画+確認テスト」を配信し、その後小テストを実施。小テスト内容の7~8割はチェックテストからで、2~3割は1年次の教材から引用。既に宿題で確認テストには取り組んでいるので、類問であるチェックテストを使用。また選択問題のほかに「自分で考えて書かせる」タイプの問題も出題し、バランスを取っています。
この確認テストは平常点にも加味しているので、生徒も真剣に臨んでいるようです。また、これらの週ベースの確認テストや定期テストの範囲に、1年次の復習要素を含めることは、既習範囲の定着にも役立っています。生徒の講義動画の視聴スタイルは、先に確認テストを行い、わからなかった箇所のみを見る反転スタイルを採用しています。時間を効率的に使うには、このようなやり方も良いのかもしれません。
また、各教科のスタディサプリの活用頻度や宿題の分量は、担当教員の裁量に任せています。提出をしない生徒に対しては、担任から声かけ。教科の担当が未提出の生徒をリスト化して担任に渡し、担任から直に生徒へ声かけしてもらう流れです。改善が見られない生徒に対しては、居残り補習をさせるケースもあります。
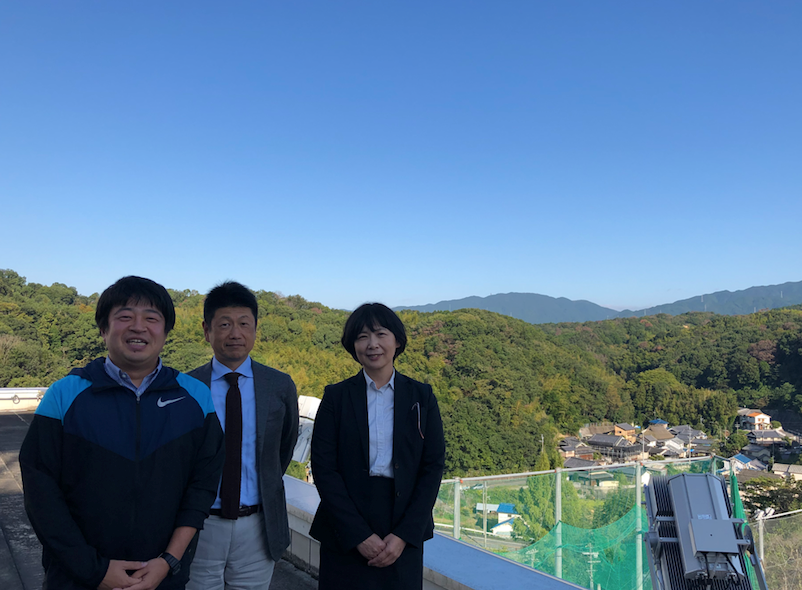
スタディサプリの導入以降、生徒にも変化が現れ始めました。理科では、教師への質問量がかなり減りました。教員から生徒に対し、「質問に来る前に、必ずスタディサプリの講義動画を見よう」と伝えたところ、効果はてきめん。生徒が言うには「動画の内容でほとんどの疑問が解決してしまう」とのこと。また、数学においては、スタディサプリの活用によって生徒の自学自習の時間が増えたり、休みがちな生徒においては、講義動画を見ることで授業に遅れをとらずに済んだという報告があがっています。英語でも、前年度より生徒の理解度が高まり、授業でくり返し説明する場面がかなり減ったそう。スタディサプリは講師陣の話が面白く、上位層の生徒には知識欲を刺激し、下位層の生徒には自学のきっかけを与え、様々な面から生徒たちの学びに一役買っているようです。
教員として感じるスタディサプリの利点は、生徒の進捗状況をいつでも把握できること。データ上で生徒の点数がチェックできるのも良いですね。英語ではスタディサプリの導入後、生徒の学習時間と小テストの結果に相関関係があることを発見しました。上位層はきちんとスタディサプリに取り組んでいるのに対し、中間層以下は取り組み不足な傾向が顕著なのです。このようにデータで可視化することによって、どの生徒に何をサポートすべきかが明確になるため、以前より指導にかける時間を効率的かつ効果的に使えるようになりました。
教員として感じるスタディサプリの利点は、生徒の進捗状況をいつでも把握できること。データ上で生徒の点数がチェックできるのも良いですね。英語ではスタディサプリの導入後、生徒の学習時間と小テストの結果に相関関係があることを発見しました。上位層はきちんとスタディサプリに取り組んでいるのに対し、中間層以下は取り組み不足な傾向が顕著なのです。このようにデータで可視化することによって、どの生徒に何をサポートすべきかが明確になるため、以前より指導にかける時間を効率的かつ効果的に使えるようになりました。
学習において少しでも多くの成功体験を。
自学自習を習慣化させるサポートを促進していきたい
今後は学校として、スタディサプリの活用をさらに促進し、自ら学習に取り組む生徒をもっと増やしたいと思っています。上位層の生徒には自分に合った学びを自ら深めてもらい、下位層の生徒には学びのきっかけを与えていきたい。下位層の生徒は、時間や手間がかかる学習を嫌がる傾向にありますが、スタディサプリの講義動画は、テンポも良く、講師の話も面白いので、何度か視聴してもらえば義務ではなく「楽しみ」から学ぶようになってくれるはず。さらに、動画を視聴すれば、テストの点まで上がるかもしれないという特典まであるのですから、見ないわけにはいきませんよね。
教員として、そんな成功体験のサイクルを作り、生徒の自学自習を習慣づけ、軌道に乗せるサポートをしていきたいと思っています。あとは、長期休暇などでも宿題配信を開始し、普段サポートができていない生徒の活用を促していけたら良いですね。スタディサプリを受験用のツールとして利用するなど、学校としてできることはまだたくさんあり、これからが楽しみです。
教員として、そんな成功体験のサイクルを作り、生徒の自学自習を習慣づけ、軌道に乗せるサポートをしていきたいと思っています。あとは、長期休暇などでも宿題配信を開始し、普段サポートができていない生徒の活用を促していけたら良いですね。スタディサプリを受験用のツールとして利用するなど、学校としてできることはまだたくさんあり、これからが楽しみです。
清教学園高等学校(大阪府)
学科:英語科・数学科
生徒数:1学年408名 2学年362名 3学年382名
生徒数:1学年408名 2学年362名 3学年382名

ページ内容は2020年1月時点の情報です。
この事例で取り上げられたサービス
関連事例
|CONTACT|
スタディサプリ学校向けサービスの導入に関する
ご質問・ご確認は、お気軽にお問い合わせください。
ご質問・ご確認は、お気軽にお問い合わせください。
就学別スタディサプリ
リクルートグループのサービス
- 転職ならリクナビNEXT
- 転職支援ならリクルートエージェント
- 女性の転職情報とらばーゆ
- 就職はリクナビ
- 就職活動はリクナビ
- 就活はリクナビダイレクト
- リクナビ派遣
- 派遣会社のリクルートスタッフィング
- 独立・開業のアントレnet
- バイト探しフロム・エーナビ
- アルバイト情報タウンワーク
- 求人転職サイトはたらいく
- フロム・エーキャリア
- 医師求人ならリクルートドクターズキャリア
- 看護師求人ならナースフル
- ケイコとマナブ.net
- じゃらんnet
- 海外旅行ならエイビーロード
- 結婚式ならゼクシィ
- 妊娠-出産-育児はゼクシィBaby
- 通販ならポンパレモール
- 不動産・住宅情報ならSUUMO
- SUUMO賃貸
- 不動産会社検索ならスマッチ
- 住宅相談はスーモカウンター
- 中古車ならカーセンサー
- ホットペッパーグルメ
- ホットペッパービューティー
- 人間ドックのここカラダ
- 海外求人・海外転職はRGF
- 家具インテリアのタブルーム
- コード評価はCodeIQ
- ゴルフ場予約じゃらんゴルフ
- POSレジアプリならAirレジ
- リクルートカード
- 関連サイト
- グループ企業一覧
- ISIZE
(C) Copyright 2020 株式会社リクルート All rights reserved.